ご承知の通り、政府は概ね10日間(3月19日)のイベント等自粛を要請しましたので、感染拡大防止対策を再度延長実施します。
なお、子育て支援「コアラのおへや」は3月31日までお休みします。
保護者の皆さま、利用者の皆さまにはご理解とご協力をお願いします。
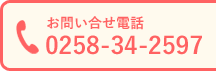

園長日誌
新型肺炎感染拡大防止について3月2日以降の対応は以下のファイルを開いてご確認ください。
保護者の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、子どものいのちを第一に且つ保護者の負担を最小限に考えての対応ですので、何卒ご理解とご協力をお願いします。
年度の最後を飾る大きな行事、お遊戯会が終わりました。
時間も労力もお金もかけて実施するので大きな達成感を得られます。
多少のミスもありましたが、例年と少しアレンジを変えたこともあり、観る側は新鮮さもあったようで、概ね好評の意見をいただきました。
裏方はというと、いつもと違う状況にバタバタで近年では一番疲れました。
園児の中には本番が一番良かった子もいれば、練習で一度も間違えなかった子が本番に間違ったりと、例年になく悲喜こもごもの様子でした。
本番は舞台袖から見ているのでよく見えないのですが、販売用DVDのサンプルが届いたので早速映像の確認をすると、1年の成長の差は本当に大きなものだと感じます。
お父さん、お母さんは我が子を中心にご覧になったでしょうから是非DVDで他の学年や同級生の様子も見ていただきたいです。(宣伝しているわけではありませんが)
リリックホールの大きな舞台に立つことができる経験はかけがえのないものだと思います。3月に卒園する年長児の中には2度とこのような舞台に立つことがない子もいるのではないでしょうか。
この幼児期は子どもだけでなく、子育てしている親にとっても実に有意義な時期とも言えます。
子どもの成長を目の当たりにし、大きな喜びを感じられるのは今が最高かもしれません。
お遊戯会前の報告で一ついい忘れたことがあります。
認知能力と非認知能力の話をしましたが、認知能力は20代前半から徐々に衰えます。ところが非認知能力は一生涯高めることができるのです。
子も親も育ちあう姿が望ましいですね。
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
さて、年の終わり近づく12月にOECDの学習到達度調査(PISA)の結果が発表されました。PISA調査は15歳児を対象に読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの三分野について、3年ごとに本調査を実施しています。
今回の調査では読解力の低下がわかり、特に判断の根拠や理由を明確にしながら自分の考えを述べることなどについては、引き続き課題が見られることも分かりました。
ではどのような取り組みをしたら読解力が高くなるのでしょうか。
幼児期について考えます。
そもそも自分の考えを言葉で伝えることは幼児期から始まります。乳児期の子どもがお友だちを噛むことがありますが、噛む理由の一つに言葉で自分の気持ちを表現できないことが挙げられます。時々幼児期に入っても噛む子がいますが、語彙量が低い子にその傾向が見られます。
ですから幼児期においてまず語彙量を増やすことが大切です。
ところが現代の日本では家庭環境によって大きく差が出ていると言われています。実際に今回の調査でも読解力が全体に低くなったわけではなく、低い層が増えたために全体として低下したと言われています。教育格差と言ってもいいのかもしれません。
ここで質問です。
皆さんのご家庭の壁にカレンダーや時計はありますか。
子どもにたくさん話しかけていますか。
新聞や本はありますか。
絵本や児童書の読み聞かせをやっていますか。
共働き率の高い新潟県では読み聞かせはハードルが高くなりつつありますが、せめて子どもの目につくところにカレンダーや時計を掛けるぐらいはできるはずです。
スマホの中ではこどもの目に触れることはありません。
核家族化進む中、会話の量も減っています。
日常的に聞く語数の差は、3歳に達するまでに最大で3000万語差がつくとも言われています。
まずは今すぐ子どもに声をかけましょう。

