今年度より始めました報恩感謝祭、略して『おんフェス』、次年度も開催することになりました。
開催日は令和7年6月7日(土)です。
創立60周年を記念して、子どもたちに大人気エビカニクスでおなじみのケロポンズをゲストに迎え、楽しい子ども向けコンサートも開催します。
また、フリマやキッチンカー、ワークショップの募集も行ないますので、興味のある方、まずはご連絡ください!
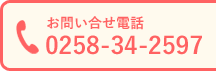

園長日誌
現在わたしは新潟県私立幼稚園・認定こども園協会の保育教諭研修委員会委員長を仰せつかっています。先日、委員会主催のオンライン研修会を開催しました。平日にもかかわらず、県内から100名を超える参加があり、また講師の掛札逸美先生の軽快な話術に引き込まれ、参加者から大変好評でした。
特に参加者全員で実施した実践的なワークショップでは、掛札先生も驚くぐらい様々な意見が出て大変有意義な研修となりました。
今回の演題は「安全と保育の質を上げるための園内コミュニケーション」として、保育においてコミュニケーションの質が大変重要だと学ばさせていただきました。その中で一番印象的だったことをご紹介します。
「人間関係✖ → 人間環境〇」
人間の脳はもともと「つい」「うっかり」、隙あらば「ぼんやり」してしまうそうです。
確かに人の話を聞いているようで、聞いていないときってありますよね。ぼんやりしている人は、ぼんやりしているのだから、自分がぼんやりしていることに気づかないのです。ついつい「ぼんやりしないで!」って言いたくなりますが、それでは関係が壊れてしまうだけです。
そんなやりとりから人間関係がうまく行かなくなるわけですが、人には馬が合う合わない、好き嫌いがありますから、職場のすべての同僚と良好な人間関係を築くことはやはり並大抵なことではありません。保護者も同様です。
そこで大切なのは、人間環境を整えること、つまり伝え合うシステムを構築することでコミュニケーションの質を向上させればよいわけです。
例えば、「おかしい」「危ない」「わからない」と思ったらすぐに尋ねられる環境づくり(仕事なのだから目上、目下は関係ありません)。また、正しく情報を伝えるための工夫(復唱や記録の仕方など)があげられます。
仲が良く馴れ合いになってもだめ、上下関係が厳しすぎてもだめ、保育は感情労働と言われますが、どうしたら子どもの安全を守れるのか、保育の質をあげられるのか、具体的なルール(システム)を職場で話し合って決める(コミュニケーション)ことが大事なのだと改めて感じました。
保育の現場だけでなく、家庭でも学校でも一般の職場でも人間環境づくりがかかせないようです。
先月、県内私立幼稚園有志9名でボストンに視察へ行きました。
幼稚園5園、公立小学校1校、子ども博物館、ボストン大学教育学部とかなりのハードスケジュールでしたが、この視察で感じたことをいくつか紹介したいと思います。
■DEIという考え方
Diversity(多様性)、Equity(公平)、Inclusion(包括)が基本方針となっています。裏を返せば、この3点が現在のアメリカでは大きな問題とも言えるでしょう。
日本では園児のほとんどが日本人であり、文化の違いなどを受け入れなければならない差し迫った状況ではありません。「ホームレスの子ども」もほとんど存在しない日本では、貧富の差が以前よりも増してはいますが、アメリカとは比較にならないレベルです。日本でもインクルーシブ保育を推進していますが、予算も人材も乏しく、国家として課題と捉えていないように感じます。
いずれ日本でも大きな問題となって取り組む日がやってくることでしょう。
■STEAM教育を意識
配置基準を除く環境も内容も日本の幼児教育と差がないように感じました。むしろ我が園の先生方はよくがんばっていると再認識しました。一方ボストンの先生方はMath(算数・数学)を意識して保育を展開しています。技術立国である日本ももう少しSTEAM教育を意識する必要性を感じました。
■配置基準に大きな差
ボストンでは州の法律で6歳未満の配置基準は10:1以下(園児10名に先生1人以上)となっています。そのため、すべての園で園児6,7人名に先生1人ぐらいの割合で配置されていました。
日本は4,5歳児で25:1、3歳児で15:1、2歳児で6:1です。日本の先生は本当にがんばっていますが、やはり配置基準が世界基準より大きく乖離しているため、これ以上の保育の質の向上はかなり難しいと思います。
■開園時間
ほとんどの園が夕方5時半ごろまでに閉園します。日本の認定こども園、保育所では11時間以上の開園が義務付けられています。
前述の配置基準、長時間保育が日本の子どもに及ぼす影響は計り知れません。
そして小中学校では過去最高の不登校児童数です。少子化なのにです。
経済優先の保育制度がこの国を亡ばすのではないかと不安になります。
主だったものを挙げましたが、別の機会で保護者の皆さまには報告したいと思います。また、他にも細部において今回視察で得たものはたくさんありますので、早速普段の保育に活用したいと思います。






ハイクオリティな幼稚園から公立幼稚園、森のようちえん等を視察。ボストン大の教授陣と意見交換。
当園では学年ごとのクラス編成となっています。
担任と園児との信頼関係の確立、同年齢の子どもたちと遊ぶ楽しさや、仲間意識の構築が大切だと考えるからです。
6月より毎朝、のびのびタイムを設けました。
のびのびタイムは、3歳児から5歳児がどこでも誰でも何をして遊んでもよい時間です。自由遊びの充実と異年齢交流を目的にしています。
最初はぎこちなく、あまり交流もできていませんでしたが、あえて声掛けをせず、子どもたちがやりたい遊びができる環境づくりに徹してきました。
しばらくすると、3~5歳児だけでなく、2歳児や乳児クラスに遊びに出かける子どももいたり、徐々に異年齢で遊ぶ姿が見られるようになりました。
10月に入ってからは週に1回、ロングのびのびタイムも実施しています。
時間が長くなったことで、遊びに夢中になる時間が増えたり、様々な遊びに挑戦する姿が見られるようになってきました。
年長者がいいお手本となって、遊びの幅が拡がり、お片付けも積極的に手伝う姿が増えてきました。また、年少者を思いやる気持ちも育まれてきているようです。
子どもたちは横のつながりも縦のつながりも当たり前に受け止められる、つまり誰とでもコミュニケーションがとれ、対話ができる一歩を踏み出しました。
自己肯定感を育む要素として、よく「ほめる」ことが大切です。
自己肯定感の高いアメリカの子どもたちは、
①子どもが自分の考えを外に出した時
②何か挑戦しようと自発的に動いた時
によくほめられています。
言葉がけも、「よく思いついたね」「話してくれてありがとう」「ナイストライ」「あなたの○○が好き」など肯定的な言葉がけ、特に上手下手、成功失敗に関係なく、こどもの行動を認める言葉がけが多いです。
ついつい、「上手にできたね」などと口にすることがありますが、これだとさらなる努力を促すことに繋がらない可能性があります。
つまり、結果ではなく、過程をほめることが重要です。
一方、「しかる」はどうでしょうか。
時々、しからない子育て、しからない保育などの言葉を耳にします。実際、本当にしからずに育ったらどうなるでしょうか。
乳幼児期はまだしも成長するにつれて、困難に直面した時に感じる不安や恐怖、不満を制御する能力が育たず、一見、自己肯定感があるように見えますが、物事に挑戦する意識は低くなってしまいます。
つまり、周囲のせいにしたり、注意されても注意した人が悪いととらえてしまうことになりかねません。
当園では、できないからといって「しかる」のはやめよう、相手を傷つける(傷つける恐れがある)とき、自分が怪我する(怪我する恐れがある)ときは、しっかりとしかろうと先生方には伝えています。
では、遊びの邪魔をしたり、ルールを破ったりしたときはどうしましょうか。
私は僧侶でもありますので、「ほめる」「しかる」にもうひとつ加えて「さとす」をお願いしています。
遊びの邪魔をした時を例にしますと、
①なぜ、他の人の遊びを邪魔したのか
②邪魔されたお友だちはどんな気持ちなのか
③自分が邪魔されたらどんな気持ちになるか
善悪の区別はほぼ乳幼児期で決まります。規範意識もほぼ同様です。
大変時間がかかることですが、自分で考えて納得しないと本物の自己肯定感は育まれません。
しっかりと愛情をもって、「ほめる」「しかる」「さとす」で親子間の愛着を形成していきましょう。
間違ってもほめすぎ、しかりすぎ、絶対に暴力もいけません。

