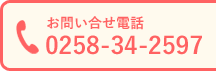平成29年度に改定された教育要領の目玉は何といっても「主体的、対話的で深い学び」といってよいでしょう。10年ごとに改定されることから、次の改定まであと1年5か月です。漏れ聞く話ですと大幅な改定はなさそうですが、この数年間、小中学校の不登校、校内暴力、自殺は増える一方で、この国の未来を危うく感ずることがあります。
令和5年に示された教育振興計画ではウエルビーイング(日本語では「持続的な幸福」と表現されることが多い)について、獲得的ウエルビーイング(自己肯定感・自己表現など)、協調的ウエルビーイング(人とのつながり・利他性・社会貢献意識など)の両者のバランスが重要だと示されました。
主体性に囚われるあまり、子どもたちに自由な保育を推奨する学者もおりますが、現場の保育者がよく学んで取り組まないと、自分勝手な人間を育む保育になる危険性を多く含んでいます。子どもたちの自発的な遊びを自由にさせるのではなく、生活に繋がるようにうまく誘導することが求められ、それには保育者の質の向上が欠かせません。
さて、私たちの幸福とはなんでしょうか。
少なくとも他人から与えられるものではなく、自分で感じるものであると言えます。
そのために必要な育みとして「自己肯定感」が挙げられます。しかしながら、それだけでは幸福を感じられず、前述の通り「人とのつながり」、つまり自己有用感(人の役に立つこと)が大切です。園において集団、つまり仲間と育つ意味はそこにあるのではないでしょうか。
年齢に応じて、子どもたちの発表や発言する場面を設けたり、縦割り保育やコーナー保育、空間環境の工夫をしたり、運動会などの園行事を通して、決して一つにとらわれることなくバランスよく取り組んでいくことが重要であり、子どもたちが幸福を感じるための土台作りになると取り組んでいます。