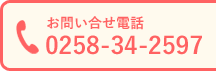先日、ECEQ【イーセック】(公開保育を活用した幼児教育の質の向上システム)に参加してきました。当園では平成30年、新潟県内で初めてECEQを実施、私自身もコーディネーター研修を受け、今までにコーディネーター2回、ファシリテーターを3回務めさせていただきました。
今回はファシリテーターとして参加しましたが、担当したクラス担任の先生からこんな質問を受けました。
「子どもたちにどこまで関わって教えていいのか」
教育要領に記載がある「主体的、対話的で深い学び」を実践するうえで、よく直面する悩みです。保育のそれぞれの場面においてどこまで関わるのか、教えたらよいのか難しい問題です。手をかけすぎてもいけないし、見守るだけでは活動が発展しません。
問題を解決する手立てとして、①問題の把握、②問題の理解、③解決策、対応策を協議すると進めていくわけですが、この場合、何が問題かといえば、子どもが主体的かということがまず挙げられます。そのうえで本来ならば子ども同士対話で解決に向けて進められればよいのですが、思うように進まないことがあり、遊びの連続性や発展に繋がらずに終わってしまうのではないかと危惧しているわけです。
私の幼少期、近所にはたくさん子どもがいました。全国には同期が200万人いる世代ですから、幼稚園児も小学生も一緒になって毎日遊んだものです。
大人から遊びを教わることもなく、近所の年上のお兄さんお姉さんのまねをしたり、ときには一緒に遊んでいるうちに遊びを覚えていきました。同じ遊びはすぐに飽きてしまいますから、自分たちで面白くなるようにルールや遊び道具を作って、日が暮れるまで遊んだものです。
ここまでやるとケガをするとか、相手が傷つく(心や体)とか、自然と学んでいきました。
いまはどうでしょうか?
うちの近所では町内子ども会活動もままならないほど少子化が進み、安全上の問題から学校が終わると低学年は放課後児童クラブに直行です。高学年になると習い事やスポーツ少年団など忙しそうです。遊びを教えてくれた少し年上のお兄さんお姉さんを近所で見かけることが難しい現状です。
誰が子どもたちに鬼ごっこやかくれんぼ、ビー玉遊びなど挙げればきりがないほどのたくさんの遊びを教えてくれるのでしょうか。
現代の保育者は、少し年上のお兄さんお姉さんの役割も求められているのではないでしょうか。