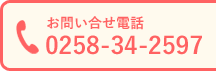現在わたしは新潟県私立幼稚園・認定こども園協会の保育教諭研修委員会委員長を仰せつかっています。先日、委員会主催のオンライン研修会を開催しました。平日にもかかわらず、県内から100名を超える参加があり、また講師の掛札逸美先生の軽快な話術に引き込まれ、参加者から大変好評でした。
特に参加者全員で実施した実践的なワークショップでは、掛札先生も驚くぐらい様々な意見が出て大変有意義な研修となりました。
今回の演題は「安全と保育の質を上げるための園内コミュニケーション」として、保育においてコミュニケーションの質が大変重要だと学ばさせていただきました。その中で一番印象的だったことをご紹介します。
「人間関係✖ → 人間環境〇」
人間の脳はもともと「つい」「うっかり」、隙あらば「ぼんやり」してしまうそうです。
確かに人の話を聞いているようで、聞いていないときってありますよね。ぼんやりしている人は、ぼんやりしているのだから、自分がぼんやりしていることに気づかないのです。ついつい「ぼんやりしないで!」って言いたくなりますが、それでは関係が壊れてしまうだけです。
そんなやりとりから人間関係がうまく行かなくなるわけですが、人には馬が合う合わない、好き嫌いがありますから、職場のすべての同僚と良好な人間関係を築くことはやはり並大抵なことではありません。保護者も同様です。
そこで大切なのは、人間環境を整えること、つまり伝え合うシステムを構築することでコミュニケーションの質を向上させればよいわけです。
例えば、「おかしい」「危ない」「わからない」と思ったらすぐに尋ねられる環境づくり(仕事なのだから目上、目下は関係ありません)。また、正しく情報を伝えるための工夫(復唱や記録の仕方など)があげられます。
仲が良く馴れ合いになってもだめ、上下関係が厳しすぎてもだめ、保育は感情労働と言われますが、どうしたら子どもの安全を守れるのか、保育の質をあげられるのか、具体的なルール(システム)を職場で話し合って決める(コミュニケーション)ことが大事なのだと改めて感じました。
保育の現場だけでなく、家庭でも学校でも一般の職場でも人間環境づくりがかかせないようです。